大げさな表現かも知れませんが、世の中、ネガティブは悪!ポジティブは善!みたいな雰囲気があると思います。
HSPさんは、0か100かで考えやすい脳です。
自分がネガティブになったとき、ネガティブになっている自分に罪悪感100%を感じてしまいませんか?
誰が、悪いといったわけでもないのに、なんだか、ネガティブになっている自分をつい、せめてしまう、ネガティブでも「まぁいいかと」思えないのが、HSPさんの生きづらさのひとつだと思います。
HSPさんは、たくさんのことに気付きます、たくさんのことを感じます、自己評価が低いことも重なって、自分ができるのに、なぜこの人はできないの?とか、「こうするべき!」のような考え方も多いので、もぅどうして…とイライラして、イライラしている自分にもイライラしてしまって。
つい、人に言った一言が、あんな言い方すべきでなかったかも、どうして自分はあんな言い方をしてしまったのだろうとか、また逆に、どうしてあんな言い方をされなければならなかったのだろうか、など、考えたら夜も眠れず、眠れない自分がまた嫌になって。
ネガティブから抜け出したいのに、ネガティブにとらわれてしまって、気持ちが切り替わらない自分が、情けなくなってしまって、このネガティブループ、HSPさんあるあるだと思います。
人間はネガティブを感じやすくできている

そもそも人間は、ネガティブに対してより反応しやすく、記憶しやすくなっています。
種の保存で、安全なことは覚えておかなくてもいいけれど、危険なことはちゃんと記憶して対処できるようにしておかないといけなかったからです。
けれど、ネガティブにより反応しやすくなるのは、種を保存するためでであって、決して生きづらくするものではないはず。
ポジティブ思考の強要は2回ダメージがある

それでも、ポジティブでいようと、ポジティブに生きる方がよいという傾向があります。
しかし、無理にポジティブ思考になろうとすることは2回、心にダメージを受け、心の回復を妨げているといいます。
1回目は、ネガティブになってしまった自分を責める。
苦しみを感じている自分を嫌悪し、苦しいときでも笑うことができない人は、ダメな人間だと思うこと。
2回目は、ネガティブになっていることから、立ち直れない自分を責める。
なかなかネガティブから抜け出せず、ポジティブ思考になれない自分に後ろめたさを感じ、罪悪感を抱いてしまう。
また、無理にポジティブな言葉を使って自分を励ましていると、逆に落ち込んでしまうそうです。
落ち込んでいるときに、落ち込むのは自然なこと、心が正直な状態です。
むしろ、落ち込んでいるのに、ポジティブになれる方が、不自然です。
必要なのは、ネガティブを受け止めること
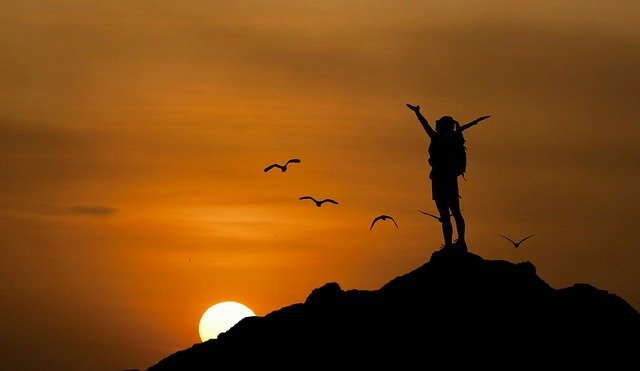
今、自分は落ち込んでいるんだ、としっかりネガティブを自分自身で受け止め、眠れぬ夜なら、眠れないなぁと受け止める。
そして、しっかり考える。
自分が、何に対して落ち込んでいるのか。
HSPさんは、自分が疑問に思ったことは、とくに人に対する、態度や考え方などを、自分が納得するまで、相手が白なのか黒なのか考えることがあると思います。
自分は、こんなにまわりのことを考えて動いているのに、まわりは自分をわかってくれない。自分はまわりを良くしたいだけなのに、何も伝わらない、くやしい気持ちを多く感じると思います。
眠れないくらいネガティブになっているときは、脳の扁桃体が優位になっているので、扁桃体の興奮を抑えるために、たくさん考えることで、前頭前野が優位になって、扁桃体を抑えることができます。考えるときは、できるだけ大きな視野で、相手も自分も宇宙の一部くらいまで大きな視野でも考えてみると、想像力を使うと前頭前野がたくさん働きます。
映画「グッドウィルハンティング」で、心理カウンセラーのショーンが、ウイルに初めて会ったとき、怒りと悔しさで、何日か眠れない夜を過ごしたけれど、たくさん考えて、納得する答えがでたとき、ぐっすり眠れたとウイルに話すシーンがあります。
映画の話ですが、心と向き合う仕事をしていても、怒りや悔しさで眠れないことも、あるのですもの、日々、感じることの多いHSPさんが眠れなくなるのも、当然!そう考えれば、少し気をラクに、ネガティブを受け止めることができると思います。
ネガティブと共存していく

HSPさんは、感じることが多すぎて、ネガティブを感じることも多いせいで生きづらさも感じてしまいます。
人が人に腹を立てるときというのは、自分は絶対正しい!と思っているときだそうです。
だとしたら、HSPさんも、わざと、気付いたことを見て見ぬふりをしてみるのも、いいかもです。
そしたら、相手だけが間違っている!という感覚がすこしうすれ、自分も見て見ぬふりしたから、とそもそものイラ立ちが少し減るかもしれません。
そうは言っても、なかなか気付いていて、行動しない自分にも腹が立つかもしれませんが、「グレーゾーン」を身に付ける練習だと思って、自分の身を守るために、切り捨てるところは切り捨てるのも大切かもしれません。
感じたことを感じたままに受け止めて、自分の感情とちゃんと向き合うことが自分にはできる!と信じていれば、ネガティブも怖くありません。
人は、どんな感情をいだいたとしても、最後には必ず、セロトニンという精神を安定する神経物質がでます。ずっとネガティブでいることもできないし、ネガティブの後には、必ず安定した気持ちになれる仕組みになっています。
本のご紹介―「感情」の解剖図鑑 苫米地 英人
「感情」の解剖図鑑 苫米地 英人
上手く感情をコントロールするには、感情について知ることか必要。
感情について、「この感情はどういうものなのか」を解説してくれていて、その感情に対する対処法も書いてくれている本です。
最後までお付き合い下さりありがとうございます。



コメント